|
上に抜き書きしただけでは物足りないので、下にあえて一部を要約させていただいた。
( 一部要約)
「1600年代半ば頃、イギリスを中心にヨーロッパではペストの大流行と、気候の寒冷化による飢饉が襲った。1640年代から1710年代にかけての70年間は寒冷化が甚だしく、この期間をマウンダー極小期(Maunder Minimum) という。小氷河期をもたらした原因は太陽活動が異常に衰退したことにある。
太陽のウオルフ黒点数※(相対黒点数)は11年周期で増減を繰り返しているが、この期間は太陽表面に黒点がほとんど見られず、そのことを発見したマウンダーの名を取ってマウンダー極小期と名付けられた。小氷河期に入るとヨーロッパでは農業は衰退して飢餓に見舞われ、その上にペストが大流行して人々は死の恐怖に直面した。
不安や恐怖の中で人々はいかに巧く死ぬかを考えるようになり、それが人間観へと発展してやがてイタリアルネッサンスが生まれた。ルネッサンスはアルプスを越えてフランス、ドイツに広がり、さらに宗教改革へと展開していった。」
太陽黒点の運動が気候変動の引き金となって、疫病などの災いをもたらし、ひいては人々の思想にまで影響を及ぼす。ドラマティックな連鎖反応を、歴史上の偉人たちの名を挙げながらつぶさに描いた本書は、地球温暖化が声高に叫ばれる今だからこそ、読んでおきたい。
(気象予報士・森川達夫)
|
参考までに、最近のウオルフ黒点数(※)は以下のグラフの通りである。
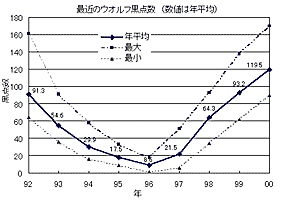
※ウオルフ黒点数…黒点群の数を10倍し、それに観測した黒点の数を加えた値
(参考) 理科年表 平成14年2002 国立天文台編(丸善)より
|
|