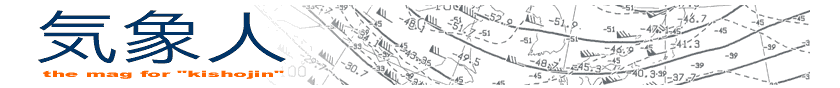10-1. 当時の気象協会の主な仕事1
(1) 天気図の作成
午前9時のアジア太平洋天気図と3時間ごとの極東天気図(B4判)のプロットから解析までを行っていた。
当時、気象協会には気象電報のテレタイプは無かったため、予報部通報課の複写の電報を頂いて来てプロットしなければならない。この気象電報を取りに、通報課へは何度も足を運ばなければならなかった。
(2) 新聞社へ新聞天気図原図の提供
アジア太平洋天気図は午前9時から6時間ごと、極東天気図は3時間ごとに予報官によって作成される。
テレタイプの気象電報を国際式から日本式に直し、新聞天気図に各地の風向風力、天気、を記入する。そして、アジア太平洋天気図をB5判に縮小した専用の天気図用紙に、予報官が解析する等圧線を素早く転写してくるのである。
それを原図にして、新聞社専用のトレッシングペーパーの天気図用紙に鉛筆で移し替える作業である。書き上がった天気図は、各新聞社が取りにくるのである。当時の新聞社のお使いさんは、ハーレーダビッドソンやジープであった。
(3) 配布用天気図の作成
朝6時の日本式の天気図をガリ版で謄写印刷し、丸の内界隈に点在する船会社やヘリコプター会社などへ自転車で配達するのである。
(4) NHK-TVへの天気図および原稿の作成
NHK専用のテロップに天気図の等圧線、天気分布図は、お天気マークをゴム印で押して作り、アナウンサーとディレクター用の放送原稿を作成し、NHKまで持参する。
天気図の等圧線は、単曲線烏口で描くのであるが、不器用な人はこの烏口がうまく使えず大変な作業であった。
放送原稿は、カーボン紙を挟んだ薄い原稿用紙を使用して作成し、お昼の天気予報番組に間に合うよう、NHK(当時は千代田区内幸町)に届けるのである。
原稿が出来上がると、往復25円の都電の回数券をもらい、錦町河岸停留所(現在の気象支援センター前)から都電に乗り、内幸町を往復するのである。
夕方の天気予報番組の場合は、予報官(A当番=アジア太平洋天気図担当)が作成した解説図(翌日9時の予想天気図)が追加される。夕方は、NHKに届けたあとは帰路に就く。
(5) ラジオ東京(現TBSラジオ)気象現況生放送
昭和31年6月1日からラジオ東京(KRT)の毎時間時報のあと、ニュースに続いて20秒から30秒くらいの気象現況の生放送が始まった。
協会内に特設スタジオが出来るまでの間、しばらくは有楽町毎日新聞社内にあったラジオ東京のスタジオからの生放送であった。
当初の放送は、近藤さんと渡辺さんの2名が担当した。半年後位に協会内にスタジオが完成した。
しかし、当時の放送用機材(アンプ)は全て真空管であった。機材自体大変大きなもので、放送の10分前に電源を入れて真空管を暖めておかないと放送が出来ない状態であった。
この気象現況の生放送が実現するまで、創立者の毛利理事の苦労は計り知れないものがあった。
当時、ラジオ東京の担当者は浜口ディレクターで、毛利理事はラジオ東京に日参したそうである。
ちなみに、昭和31年6月1日からは、中国大陸の気象管制が解除され、気象電報が解禁となった。それまでの天気図には朝鮮半島やシベリア(ソ連)、台湾、香港のデータは記入されていたが、中国大陸のデータは全く記入されていない。
日本の西に位置する中国大陸の気象電報が全て入電するようになり、予報もしやすくなった時代でもあった。
数年後、ラジオ東京では、夕方4時20分から「東京ダイヤル」という新しい情報番組が始まった。
担当のキャスターは、当時、映画館で上映するパラマウントニュースのナレーションを行っていた人気アナウンサーの竹脇昌作(俳優竹脇無我の父親)で、イントネーションの無い独特のしゃべりで口調で、特に奥様方には「マダムキラー」として大変な人気であった。
午後4時20分になると、「ツー・ツツー・ツー・ツー・ツーツー」というモールス信号がしばらく流れ、「マツダランプや芝浦モートルでお馴染みの東京芝浦電気がお送りする東京ダイヤル」というタイトルメッセージで始まり、コマーシャルが流れた後「只今の時刻、4時21分30秒、」と言うナレーションで番組がスタートする、
「では早速今日のニュースから」と言って名調子のニュースが読み上げられる。この番組中にも天気予報の枠があり、30秒程度の気象現況の生放送を行った。
しかし、昭和38年、皇太子(現天皇陛下)美智子妃殿下のご結婚の実況放送の後、竹脇昌作アナは、心労のためか、残念ながら自ら命を絶ってしまった。
一方、文化放送(JOQR)では、専用電話(磁石式の通称ガラ電)による「お天気おじさん」と言う生放送も始まった。
午前9時のアジア太平洋天気図と3時間ごとの極東天気図(B4判)のプロットから解析までを行っていた。
当時、気象協会には気象電報のテレタイプは無かったため、予報部通報課の複写の電報を頂いて来てプロットしなければならない。この気象電報を取りに、通報課へは何度も足を運ばなければならなかった。
(2) 新聞社へ新聞天気図原図の提供
アジア太平洋天気図は午前9時から6時間ごと、極東天気図は3時間ごとに予報官によって作成される。
テレタイプの気象電報を国際式から日本式に直し、新聞天気図に各地の風向風力、天気、を記入する。そして、アジア太平洋天気図をB5判に縮小した専用の天気図用紙に、予報官が解析する等圧線を素早く転写してくるのである。
それを原図にして、新聞社専用のトレッシングペーパーの天気図用紙に鉛筆で移し替える作業である。書き上がった天気図は、各新聞社が取りにくるのである。当時の新聞社のお使いさんは、ハーレーダビッドソンやジープであった。
(3) 配布用天気図の作成
朝6時の日本式の天気図をガリ版で謄写印刷し、丸の内界隈に点在する船会社やヘリコプター会社などへ自転車で配達するのである。
(4) NHK-TVへの天気図および原稿の作成
NHK専用のテロップに天気図の等圧線、天気分布図は、お天気マークをゴム印で押して作り、アナウンサーとディレクター用の放送原稿を作成し、NHKまで持参する。
天気図の等圧線は、単曲線烏口で描くのであるが、不器用な人はこの烏口がうまく使えず大変な作業であった。
放送原稿は、カーボン紙を挟んだ薄い原稿用紙を使用して作成し、お昼の天気予報番組に間に合うよう、NHK(当時は千代田区内幸町)に届けるのである。
原稿が出来上がると、往復25円の都電の回数券をもらい、錦町河岸停留所(現在の気象支援センター前)から都電に乗り、内幸町を往復するのである。
夕方の天気予報番組の場合は、予報官(A当番=アジア太平洋天気図担当)が作成した解説図(翌日9時の予想天気図)が追加される。夕方は、NHKに届けたあとは帰路に就く。
(5) ラジオ東京(現TBSラジオ)気象現況生放送
昭和31年6月1日からラジオ東京(KRT)の毎時間時報のあと、ニュースに続いて20秒から30秒くらいの気象現況の生放送が始まった。
協会内に特設スタジオが出来るまでの間、しばらくは有楽町毎日新聞社内にあったラジオ東京のスタジオからの生放送であった。
当初の放送は、近藤さんと渡辺さんの2名が担当した。半年後位に協会内にスタジオが完成した。
しかし、当時の放送用機材(アンプ)は全て真空管であった。機材自体大変大きなもので、放送の10分前に電源を入れて真空管を暖めておかないと放送が出来ない状態であった。
この気象現況の生放送が実現するまで、創立者の毛利理事の苦労は計り知れないものがあった。
当時、ラジオ東京の担当者は浜口ディレクターで、毛利理事はラジオ東京に日参したそうである。
ちなみに、昭和31年6月1日からは、中国大陸の気象管制が解除され、気象電報が解禁となった。それまでの天気図には朝鮮半島やシベリア(ソ連)、台湾、香港のデータは記入されていたが、中国大陸のデータは全く記入されていない。
日本の西に位置する中国大陸の気象電報が全て入電するようになり、予報もしやすくなった時代でもあった。
数年後、ラジオ東京では、夕方4時20分から「東京ダイヤル」という新しい情報番組が始まった。
担当のキャスターは、当時、映画館で上映するパラマウントニュースのナレーションを行っていた人気アナウンサーの竹脇昌作(俳優竹脇無我の父親)で、イントネーションの無い独特のしゃべりで口調で、特に奥様方には「マダムキラー」として大変な人気であった。
午後4時20分になると、「ツー・ツツー・ツー・ツー・ツーツー」というモールス信号がしばらく流れ、「マツダランプや芝浦モートルでお馴染みの東京芝浦電気がお送りする東京ダイヤル」というタイトルメッセージで始まり、コマーシャルが流れた後「只今の時刻、4時21分30秒、」と言うナレーションで番組がスタートする、
「では早速今日のニュースから」と言って名調子のニュースが読み上げられる。この番組中にも天気予報の枠があり、30秒程度の気象現況の生放送を行った。
しかし、昭和38年、皇太子(現天皇陛下)美智子妃殿下のご結婚の実況放送の後、竹脇昌作アナは、心労のためか、残念ながら自ら命を絶ってしまった。
一方、文化放送(JOQR)では、専用電話(磁石式の通称ガラ電)による「お天気おじさん」と言う生放送も始まった。

10-2. 当時の気象協会の主な仕事2
(6)電話による天気予報サービス
昭和29年9月1日から、東京地方だけ電話による天気予報サービスが始まっていた。当時は、局番なしの222番(現177番)であった。ちなみに、時報サービスは223番(現117)であった。
天気予報サービスの録音は、気象協会の職員の担当で、大手町にある千代田電話局の5階の録音室で行われた。ここでは、時報と天気予報のサービスが行われているフロアーである。
月曜から土曜のお昼までの昼間は、中村さんという女性職員が担当し、午後5時から翌朝9時までと土曜日の午後と日曜日全日は男性職員が交代で担当した。
気象庁予報部に派遣されている協会職員から磁石式の直通電話(通称ガラ電)にて原稿を受け、下読みと原稿の長さを測り、テープの長さを決めてエンドレスのテープを作成して録音する。決められた発表時間にサービスを開始する。
ちなみに、このエンドレスの録音機や、黒くてまるで粗悪な紙のようなテープを作製していたのが東京通信工業で現在のソニーである。
東京で始まった222天気予報サービスが後に全国展開され、各地方気象台内に支部が開設されることになる。電話番号も222番から「天気になれなれ」の177番に統一されることになる。
この時の夜勤は、電話局の人と2名である。局の人の作業は時報サービスのメンテナンスが主であるが、時折時報のエンドレスアナウンステープ(只今から何時何分何秒をお知らせします)の絡み合いでサービスがストップしてしまう。警報が鳴るので、隣の予備機に切り替え、サービスを再開させるのである。
気象サービスは、切り替え時間が決められているが、天気の急変した場合には、スポット天気予報が発表され、臨時に録音し直してサービスを行わなければならない。また、台風や地震の発生、注意報、警報が発表された場合にも、すぐに録音し直し、手早く切り替えなければならない。たまに、切り替えを忘れてしまい、試聴者から古い予報を聞かされてしまった。料金を返せ等という抗議の電話も頂いたことがある。
電話局の職員との夜勤は、大変楽しみで、ウヰスキー(ニッカ角、当時300円)を鞄に入れての出勤である。
電話局の食堂で買った冷めた夕食のおかずを肴に、夜7時頃から酒盛りが始まる。
我々は4交代なので、4日おきの夜勤であったが、局の職員は大勢なので、毎回の顔ぶれが違う。中には大酒を食らう人、全然飲まない人、子供の遠足のように果物を沢山用意する人、クラリネットの練習をする人、H写真を持ってくる人、局内を遊び回って朝まで帰ってこない人、皆様ざまで、話題も豊富で大変楽しい夜勤であった。
(7) 気象台の見学案内
当時、小学生や中学生の気象台の見学が多かった。この案内の窓口を行うのが気象協会の仕事である。
現在のKKR竹橋会館入り口付近に、高さ20メートルくらいの時計塔(観測塔)があった。関東大震災にも耐え、発生時間に止まった時刻の時計塔写真は、当時の新聞や報告書などにも数多く載っている。
入り口の奥に水銀気圧計室があり、2階がベニヤで囲った事務室、3階から上は気象観測に必要な古めかしい観測機械類が展示されていた。そして屋上には、当時実際に観測で使用していた矢羽根式の風向計、3杯風速計、ロビンソン風速計(4杯)等が設置してあった。これらはいずれも風程型の風速計で、回転数の記録から風速を算出するものである。
また、ジョルダン日照計、これは直径10cm位のガラス玉で下の固定された溝に時刻を刻んだ記録紙を挟み、太陽が照ると照った時刻に焼けた記録が残る仕組みで、その長さを日照時間とするという、いたって原始的な測器である。
一方、カンベル日照計もあった。これは直径5~6cm、長さ15cm位の黒い円筒形で、真ん中辺に1mm程の穴が2つ開いている。円筒形の中に青写真の薬品処理された記録紙をセットする、朝になって太陽が昇ってくると、東側の穴から射し込んだ太陽の軌跡が焼き付けられる。太陽の南中後は、反対の西側の穴から入る軌跡が残るようになる。記録紙を強い光に当てると記録が消えてしまうので、記録紙の交換は夜間でないと行えない。
時計塔の南、皇居に面した敷地には、地上気象観測の露場があった。
当時の露場に設置してある観測機器は、すべて観測員の目視によるもので、現在のような隔測の出来る測器は全く無かった。
露場の中央に大型百葉箱(気象庁1号型)が設置され、その中には、電動ファンの付いた水銀温度計、右側が乾球温度計、左側は湿球温度計、そのほかゼンマイ式の自記温度計、自記湿度計、最高・最低温度計などがある。
観測当番者は、毎正時11分前に風速計の風程値を読みとり、温度計のファンのスイッチ入れ、湿球温度計のガーゼにスポイトで水を含ませる。
そして天気や雲などの観測を行なう。下層、中層、上層の3段階にある雲の種類、高さ、全雲量を観測野帳記入する。
また、降水があった場合には、雨量の観測も行う。現在のような転倒マスによる隔測ではなく、雨量マスによる観測である。正時1~2分前に乾球温度、湿球温度の観測、風程の観測、そして気圧計室に走り、正時に気圧を読みとる。これを毎時間繰り返す。
それに、Zタイム(グリニッジ)00時(日本時間午前9時)から3時間おきには視程観測も行う。これは地上気象観測に入る前に時計塔に駆け上がり、水平の視程を観測するもので、視程観測板というのがあり、目標となる建物や山などの距離が示されている。
観測が終了すると、観測データを整理し、気象電報(5桁づつの数字)を作成して、専用電話で通報課に送る。
そのほか何時雨が降り出したか、何時止んだか、雨の降り方強さなども常に監視していなければならない。当時の観測当番者は、かなりの重労働であった。
このような気象観測の説明や時計塔の案内窓口が仕事である。
見学者の案内は、これらの東京管区気象台技術課観測係の職員が行った。
変な話ではあるが、案内者に謝礼しなければならないので、協会では学童1人当たり5円のお金を徴収していた。今では考えられないことである。昭和39年2月、現在の気象庁ビルに移転してからは見学案内は中止となった。
昭和29年9月1日から、東京地方だけ電話による天気予報サービスが始まっていた。当時は、局番なしの222番(現177番)であった。ちなみに、時報サービスは223番(現117)であった。
天気予報サービスの録音は、気象協会の職員の担当で、大手町にある千代田電話局の5階の録音室で行われた。ここでは、時報と天気予報のサービスが行われているフロアーである。
月曜から土曜のお昼までの昼間は、中村さんという女性職員が担当し、午後5時から翌朝9時までと土曜日の午後と日曜日全日は男性職員が交代で担当した。
気象庁予報部に派遣されている協会職員から磁石式の直通電話(通称ガラ電)にて原稿を受け、下読みと原稿の長さを測り、テープの長さを決めてエンドレスのテープを作成して録音する。決められた発表時間にサービスを開始する。
ちなみに、このエンドレスの録音機や、黒くてまるで粗悪な紙のようなテープを作製していたのが東京通信工業で現在のソニーである。
東京で始まった222天気予報サービスが後に全国展開され、各地方気象台内に支部が開設されることになる。電話番号も222番から「天気になれなれ」の177番に統一されることになる。
この時の夜勤は、電話局の人と2名である。局の人の作業は時報サービスのメンテナンスが主であるが、時折時報のエンドレスアナウンステープ(只今から何時何分何秒をお知らせします)の絡み合いでサービスがストップしてしまう。警報が鳴るので、隣の予備機に切り替え、サービスを再開させるのである。
気象サービスは、切り替え時間が決められているが、天気の急変した場合には、スポット天気予報が発表され、臨時に録音し直してサービスを行わなければならない。また、台風や地震の発生、注意報、警報が発表された場合にも、すぐに録音し直し、手早く切り替えなければならない。たまに、切り替えを忘れてしまい、試聴者から古い予報を聞かされてしまった。料金を返せ等という抗議の電話も頂いたことがある。
電話局の職員との夜勤は、大変楽しみで、ウヰスキー(ニッカ角、当時300円)を鞄に入れての出勤である。
電話局の食堂で買った冷めた夕食のおかずを肴に、夜7時頃から酒盛りが始まる。
我々は4交代なので、4日おきの夜勤であったが、局の職員は大勢なので、毎回の顔ぶれが違う。中には大酒を食らう人、全然飲まない人、子供の遠足のように果物を沢山用意する人、クラリネットの練習をする人、H写真を持ってくる人、局内を遊び回って朝まで帰ってこない人、皆様ざまで、話題も豊富で大変楽しい夜勤であった。
(7) 気象台の見学案内
当時、小学生や中学生の気象台の見学が多かった。この案内の窓口を行うのが気象協会の仕事である。
現在のKKR竹橋会館入り口付近に、高さ20メートルくらいの時計塔(観測塔)があった。関東大震災にも耐え、発生時間に止まった時刻の時計塔写真は、当時の新聞や報告書などにも数多く載っている。
入り口の奥に水銀気圧計室があり、2階がベニヤで囲った事務室、3階から上は気象観測に必要な古めかしい観測機械類が展示されていた。そして屋上には、当時実際に観測で使用していた矢羽根式の風向計、3杯風速計、ロビンソン風速計(4杯)等が設置してあった。これらはいずれも風程型の風速計で、回転数の記録から風速を算出するものである。
また、ジョルダン日照計、これは直径10cm位のガラス玉で下の固定された溝に時刻を刻んだ記録紙を挟み、太陽が照ると照った時刻に焼けた記録が残る仕組みで、その長さを日照時間とするという、いたって原始的な測器である。
一方、カンベル日照計もあった。これは直径5~6cm、長さ15cm位の黒い円筒形で、真ん中辺に1mm程の穴が2つ開いている。円筒形の中に青写真の薬品処理された記録紙をセットする、朝になって太陽が昇ってくると、東側の穴から射し込んだ太陽の軌跡が焼き付けられる。太陽の南中後は、反対の西側の穴から入る軌跡が残るようになる。記録紙を強い光に当てると記録が消えてしまうので、記録紙の交換は夜間でないと行えない。
時計塔の南、皇居に面した敷地には、地上気象観測の露場があった。
当時の露場に設置してある観測機器は、すべて観測員の目視によるもので、現在のような隔測の出来る測器は全く無かった。
露場の中央に大型百葉箱(気象庁1号型)が設置され、その中には、電動ファンの付いた水銀温度計、右側が乾球温度計、左側は湿球温度計、そのほかゼンマイ式の自記温度計、自記湿度計、最高・最低温度計などがある。
観測当番者は、毎正時11分前に風速計の風程値を読みとり、温度計のファンのスイッチ入れ、湿球温度計のガーゼにスポイトで水を含ませる。
そして天気や雲などの観測を行なう。下層、中層、上層の3段階にある雲の種類、高さ、全雲量を観測野帳記入する。
また、降水があった場合には、雨量の観測も行う。現在のような転倒マスによる隔測ではなく、雨量マスによる観測である。正時1~2分前に乾球温度、湿球温度の観測、風程の観測、そして気圧計室に走り、正時に気圧を読みとる。これを毎時間繰り返す。
それに、Zタイム(グリニッジ)00時(日本時間午前9時)から3時間おきには視程観測も行う。これは地上気象観測に入る前に時計塔に駆け上がり、水平の視程を観測するもので、視程観測板というのがあり、目標となる建物や山などの距離が示されている。
観測が終了すると、観測データを整理し、気象電報(5桁づつの数字)を作成して、専用電話で通報課に送る。
そのほか何時雨が降り出したか、何時止んだか、雨の降り方強さなども常に監視していなければならない。当時の観測当番者は、かなりの重労働であった。
このような気象観測の説明や時計塔の案内窓口が仕事である。
見学者の案内は、これらの東京管区気象台技術課観測係の職員が行った。
変な話ではあるが、案内者に謝礼しなければならないので、協会では学童1人当たり5円のお金を徴収していた。今では考えられないことである。昭和39年2月、現在の気象庁ビルに移転してからは見学案内は中止となった。

10-3. 当時の気象協会の主な仕事3
(8)気象関係図書の編集・発行・販売
月刊誌「気象」、わかりやすい天気図の話、天気予報の手引、新しい航空気象、気象測器のいろいろ等の編集発行。気象庁刊行の気象月報、気象要覧、測候時報、研究時報、地上気象観測法などの販売が主であった。
昭和32年春、高田健二さんの発案でカラー版「日本の気候図」を発行することが決まり、全員で資料の収集、作図や編集作業に当たった。
全体の指揮は発案者の高田氏で、我々は休日出勤の連続であった。出勤すると高田氏から作業の指示がある。私は製図が得意だったので、版下の作成が主であった。
当時、高田氏の意気込みは大変なもので、全国に学校が何十万校あって、そのうちの1割の学校が1冊買ったとして何万冊は売れる。定価350円だからこれだけ儲かると言うのである。
全職員それを信じて一生懸命作業に当たり、昭和33年10月にやっと発刊の運びとなった。
そして全国の主な学校にダイレクトメールをかけたが、反応はさっぱりで、出来上がった本は、無惨にも露場の隅の倉庫に積み上げられることになってしまった。
当時は珍しいカラー印刷だったため、かかった印刷費は数百万円、がくんと赤字になってしまい、この時点で気象協会も倒産という最悪の事態になった。
赤字続きの当時の気象協会がなぜ潰れなかったのであろうか。そこには昔からの下町の人情深さに救われたからである。
この図書の印刷を手がけたのは、上野(台東区黒門町)にあった田中幸和堂印刷所であった。ここの田中社長は、映画「寅さん」に出てくるタコ社長(太宰久夫)を小さくしたような風貌で、当時は大変珍しい外車(ヒルマン)を乗り回わし、協会の財政事情はお見通しであった。
この社長の下町人情によって、印刷費の減額や残金の延べ払いなど措置がとられ、倒産の危機を回避されたのである。
このとき、この社長がいなければ、今の日本気象協会はなかったであろうと思われる。このような事情を知る職員は少なかった。
当時の毛利理事、経理担当の野中さんの苦労はいかばかりであったか、田中幸和堂社長に感謝したい。ちなみに、この印刷所は平成の時代に入ってまもなく廃業してしまった。
幸い、昭和33年といえば、フジテレビや日本教育テレビ(現テレビ朝日)の開局もあり、報道関係の仕事も急増して、なんとか持ちこたえた時代でもある。
(9) 調査研究関係業務
中央自動車道関連の雨量調査が始まり、やがて電力関係の立地環境調査の全盛期に向かい、調査業務が急増した。解説予報が主であった業務が調査業務に移行した時代でもある。
(10)天気図のプロットから解析
現在は、天気図のプロットも等圧線の描画もコンピュータがすべて行ってしまう。今、気象予報士は何万人といるが、自分で天気図を書ける人はどれだけ居るだろうか。
現在、テレビやラジオで気象予報士として活躍している人々のほとんどは、天気図を描いた経験を持つ人は少ないのではないだろうか。
天気予報の基本は天気図である。これほど細かな気象資料の入った物はない。世界の気象観測所で観測される観測値は、自動観測機器で得られたデータと観測員による観天望気のデータが事細かに記入されている。海上船舶からのデータには、地上観測データのほかに、風浪の向きや波の高さまで記入される。
これを読むのが気象庁の予報官や民間の気象予報士の仕事であるはずだ。
現在のようにコンピュータの無かった当時は、有線通信課、無線通信課に入ってくる気象電報は、通報課に集められ、通報課職員によって天気図用紙に記入された。
この天気図の記入は、一人でしか行得ないので、アジア太平洋天気図で約2時間半、極東天気図で約2時間ほども要した。
予報担当者(F当番)が描く天気図は、極東天気図である。北太平洋地域に対する指示報、警報を担当する予報官(A当番)が描くのがアジア太平洋天気図で、高層天気図を担当する予報官(U当番)は850mb(現在はhPa)、700mb、500mb、300mb等の天気図を解析する。北半球天気図を担当するのは週間予報の予報官であった。
気象関係の作業は世界共通であり、時間はグリニッジタイム(Z時)が基準で、日本時間の午前9時が00Z時となる。
作成られる天気図は、極東天気図が、午前9時を基準に12時、15時、18時、21時、00時、03時、06時の3時間ごとで、一日8枚が解析される。これは天気予報を発表するため時間が細かい。
アジア太平洋天気図は6時間ごとの4枚。高層天気図は午前9時と午後9時の2枚が解析される。北半球天気図は、地上および高層とも21時の1枚である
当時、気象協会では、短波放送に対する気象情報の提供のため、アジア太平洋天気図、気象現況や実況の把握のため、極東天気図型(B4判)のプロットから解析まで行っていた。
月刊誌「気象」、わかりやすい天気図の話、天気予報の手引、新しい航空気象、気象測器のいろいろ等の編集発行。気象庁刊行の気象月報、気象要覧、測候時報、研究時報、地上気象観測法などの販売が主であった。
昭和32年春、高田健二さんの発案でカラー版「日本の気候図」を発行することが決まり、全員で資料の収集、作図や編集作業に当たった。
全体の指揮は発案者の高田氏で、我々は休日出勤の連続であった。出勤すると高田氏から作業の指示がある。私は製図が得意だったので、版下の作成が主であった。
当時、高田氏の意気込みは大変なもので、全国に学校が何十万校あって、そのうちの1割の学校が1冊買ったとして何万冊は売れる。定価350円だからこれだけ儲かると言うのである。
全職員それを信じて一生懸命作業に当たり、昭和33年10月にやっと発刊の運びとなった。
そして全国の主な学校にダイレクトメールをかけたが、反応はさっぱりで、出来上がった本は、無惨にも露場の隅の倉庫に積み上げられることになってしまった。
当時は珍しいカラー印刷だったため、かかった印刷費は数百万円、がくんと赤字になってしまい、この時点で気象協会も倒産という最悪の事態になった。
赤字続きの当時の気象協会がなぜ潰れなかったのであろうか。そこには昔からの下町の人情深さに救われたからである。
この図書の印刷を手がけたのは、上野(台東区黒門町)にあった田中幸和堂印刷所であった。ここの田中社長は、映画「寅さん」に出てくるタコ社長(太宰久夫)を小さくしたような風貌で、当時は大変珍しい外車(ヒルマン)を乗り回わし、協会の財政事情はお見通しであった。
この社長の下町人情によって、印刷費の減額や残金の延べ払いなど措置がとられ、倒産の危機を回避されたのである。
このとき、この社長がいなければ、今の日本気象協会はなかったであろうと思われる。このような事情を知る職員は少なかった。
当時の毛利理事、経理担当の野中さんの苦労はいかばかりであったか、田中幸和堂社長に感謝したい。ちなみに、この印刷所は平成の時代に入ってまもなく廃業してしまった。
幸い、昭和33年といえば、フジテレビや日本教育テレビ(現テレビ朝日)の開局もあり、報道関係の仕事も急増して、なんとか持ちこたえた時代でもある。
(9) 調査研究関係業務
中央自動車道関連の雨量調査が始まり、やがて電力関係の立地環境調査の全盛期に向かい、調査業務が急増した。解説予報が主であった業務が調査業務に移行した時代でもある。
(10)天気図のプロットから解析
現在は、天気図のプロットも等圧線の描画もコンピュータがすべて行ってしまう。今、気象予報士は何万人といるが、自分で天気図を書ける人はどれだけ居るだろうか。
現在、テレビやラジオで気象予報士として活躍している人々のほとんどは、天気図を描いた経験を持つ人は少ないのではないだろうか。
天気予報の基本は天気図である。これほど細かな気象資料の入った物はない。世界の気象観測所で観測される観測値は、自動観測機器で得られたデータと観測員による観天望気のデータが事細かに記入されている。海上船舶からのデータには、地上観測データのほかに、風浪の向きや波の高さまで記入される。
これを読むのが気象庁の予報官や民間の気象予報士の仕事であるはずだ。
現在のようにコンピュータの無かった当時は、有線通信課、無線通信課に入ってくる気象電報は、通報課に集められ、通報課職員によって天気図用紙に記入された。
この天気図の記入は、一人でしか行得ないので、アジア太平洋天気図で約2時間半、極東天気図で約2時間ほども要した。
予報担当者(F当番)が描く天気図は、極東天気図である。北太平洋地域に対する指示報、警報を担当する予報官(A当番)が描くのがアジア太平洋天気図で、高層天気図を担当する予報官(U当番)は850mb(現在はhPa)、700mb、500mb、300mb等の天気図を解析する。北半球天気図を担当するのは週間予報の予報官であった。
気象関係の作業は世界共通であり、時間はグリニッジタイム(Z時)が基準で、日本時間の午前9時が00Z時となる。
作成られる天気図は、極東天気図が、午前9時を基準に12時、15時、18時、21時、00時、03時、06時の3時間ごとで、一日8枚が解析される。これは天気予報を発表するため時間が細かい。
アジア太平洋天気図は6時間ごとの4枚。高層天気図は午前9時と午後9時の2枚が解析される。北半球天気図は、地上および高層とも21時の1枚である
当時、気象協会では、短波放送に対する気象情報の提供のため、アジア太平洋天気図、気象現況や実況の把握のため、極東天気図型(B4判)のプロットから解析まで行っていた。